レポートVol.31 『日本の大地震・1891』‘The Great Earthquake in Japan‘
『日本の大地震・1891』‘The Great Earthquake in Japan’ Jean・MarieMahieu
|
『日本の大地震・1891』のような本は、まさに、明治時代の鏡である。 |
 |
|
i. |
|
 |
 |
 |
|
ii. |
||
|
iii. |
||
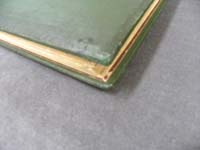 |
 |
|
iv. |
|
v. このように見ると、以上に述べてあるミルンやバルトンや、 そして、小川の道は、微妙に交差して、明治中期のこの代表的な「外国向き」の本の出版を可能にしたのである。 ある意味では、日本社会のグローバリゼーションの始まりでもある。 |
| この貴重な本をみごとに修復していただいた「書物の歴史と保存修復に関する研究会」の皆様にふかく感謝いたすところである。 | ||
 |
なお、この物語の登場人物の最後まで言わせていただければ、ミルンは、日本人である函館出身のトネ子婦人をつれて、1895年に英国に帰国して、そこで、ほぼ全世界を結ぶ地震情報ネットワークをつくることによって、イギリスを地震学のメッカにした。 |
|
|
Jean・MarieMahieu |
||


